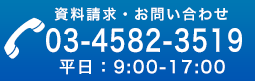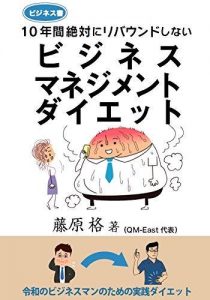歪んだ思考について考える
色々な角度・視点から物事を眺めていかないと間違った解釈、方向に行くことはいうまでもありません。
わかりやすいところでいうと熊の出没に関する反応。駆除されたというニュースの度に「熊がかわいそうだ」とか「なぜ処分した」という苦情が役所にたくさん入ります。ものの見方が一方的であることの典型的な例です。客観的には仕方ないはずなのに、自分の感情や一方的なものの見方が強くなると周囲は迷惑をします。組織の中でも相手の立場や違った視点をいくつか持ちながら判断、行動をしていかないと不要な摩擦、トラブルをかかえることもあるでしょう。最終的にはクライアントの気持ちにどれだけ寄り添えているかどうか=成果に繋がっていきます。
歪んだ思考は正式には「認知の歪み」といいます。その中身をいくつかご紹介します。
●白か黒か=0点か100点で考えてしまう・・その間にいくつもの着地点があることを理解しなければなりません。
●よいところは見ないで悪いところだけ見てしまう・・・誰にでも長所と短所の両方がありますが、短所だけを見て、この人は悪い人!と決めつけてしまうクセ。あえてよい点にフォーカスすることで違う一面が見えてきます。
●結論の飛躍=悲観的に考えてしまうクセ・・例えば、相手が返事をしてくれなかった時に、聞こえなかっただけかもしれないのに「私は嫌われている!」と勝手に思いこみ、落ち込んでしまうようなものです。
●失敗を実際よりも大げさに考えたり、成功を過少に考えてしまうような思考のクセ。同じようなものとして「マイナス化思考」というものあります。うまくいったら「こんなのはまぐれ」、うまくいかなかったら「ほらやっぱりうまくいかない」と考える思考習慣のこと。
●一般化のし過ぎ=大した根拠もないのに結論を決めつけてかかる。
●感情的決めつけ=自分の感情がそう思うからそうに決まっていると考えてしまうクセ。「そんなのは✖✖に決まっている!」その一点から降りない、譲らない人は結構いますね。
他にもありますが、こうした「認知の歪み」をまずは意識して、よりよい判断を下すための冷静さ、客観思考を持つように努めることが大切です。上司がこのような思考習慣のクセを持っていると部下は大変迷惑します。経営者は自らもそうですが、率先して組織全体で認知の歪みを修正するための投げかけやコミュニケーションを取っていくことがまずは大事です。
感動をこころに 喜びをちからに 感謝をかたちに
※この記事は2025年8月5日(火) ㈱研秀舎/QM-East 代表の藤原格によって作成されました。