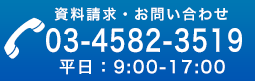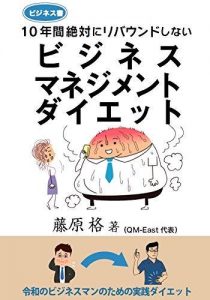組織の全体底上げを促すために欠かせない気づき
行列店に学ぶ
先日、揚げ物で名を馳せているある行列店でランチをしました。20席ほどが座れるこじんまりしたお店ですが、昼時はいつも10人くらい外に並んでいます。 ランチタイムしか知りませんが、なかなか美味しくてボリュームがあります。しかし、安くはありません。ほとんどのメニューが1000円以上です。
そして、これが売り!という強烈なUSPは見当たりません。それでもコアなファンに支えられているのでしょう、毎日にぎわっています。WEBで口コミを見ても高い評価で安定しています。サクラも嫌がらせもない口コミはすがすがすがしいものです。地味だけど本当の実力店ということでしょう。

USPについて
さて、USP(ユニークセリングプロポジション)は説明するまでもなく「独自の売り」という言葉で表されるマーケティング用語です。なにかひとつ、他の会社(店)にない際立った特徴を!ということですが、USPを求める姿勢そのものは正しいことですし、必要なものだと思います。しかし、気をつけなければならないのが、疎かになっている点には気づかず、外に向けた特徴ばかり強調していないかという点です。また特徴さえあれば普段、御客様の目に付かないところは疎かになっていても適当にカバーできるのではないか、という発想です。
飲食店であれば味や値段に特徴が出せていても、清潔感、接客態度、居心地など基本的なことがオソロかであればそれはやはり伝わってしまいます。どんなに着飾って綺麗に振舞っても性格がだらしなかったり、衣類にシミがついている、あるいは歩き方に品がなかったりすると伝わってしまうようなものです。
なぜこうした話をするかというと、基本や足元を省みないで、外に向いた華の部分ばかりにフォーカスするリーダー、経営者が意外と多いからです。経営者になると、社内はもちろんですが諫言してくれる存在が少なくなるので I’mOK, You are not OK が染み付いてしまっていると思われます。俺が会社を支えている!という自負も努力ももちろんあるでしょうが。

僅差・微差
環境整備を徹底しているある製造業の社長は掃除を通して僅差・微差を追求しているといいます。毎日集中して掃除を行っているとザラッとする感覚、日常と違う点に気がつくようになるといいます。これが大事なんだと。これに気がつくことが感性をみがくことにつながるといいます。ちょっとした違いに気づけるということは職場にも目の前に相手に対して配慮、心配りができるということでもあります。優しくなれることでもあります。社長が率先して汗をかきながら一緒に掃除をする姿勢そのもの、掃除から学ぶ感性を経営に活かしているのでこの会社に伺うと脇が締まっていると感じます。社員様がみなすばらしい対応をされます。これがこの会社のUSPそのものにもなっています。こういう会社は基本がしっかり出来ているので様々な文化が根付きやすくなります。全体底上げを行いながら、ひとつの特徴が際立っていく、というのが正しい順番とも感じます。社員が学ばない、覚えない、伸びないと思っている方はまず自ら足元を見たり、あるいは客観的にアドバイスを貰うことを習慣にしてみてはいかがでしょうか。

上記の記事は弊社の根幹となる哲学「喜びの帝王学」を基にしています。